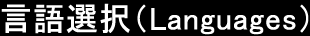■土佐錦(とさにしき)県産の酒米としては、これまで一般掛け米の「アキツホ」が広く使用されていました。 しかし、「高知県独自の開発による、より酒造適性の高い米を」という要望から、「中国81号」に注目し、試験栽培が行われました。 この品種は、もともと平成3年に主食用として検討されたものの、試験が中止となっていた米でしたが、酒造適性試験を重ねた結果、平成6年に「土佐錦」として生まれ変わりました。 「土佐錦」は大粒で吸水性がよく、粗タンパク質含有量が低いという、酒造適性を備えています。そのため、雑味が少なく、酸やアミノ酸の控えめな、淡麗辛口の土佐酒に仕上がります。 ■吟の夢(ぎんのゆめ)高知県で育てた、県産第1号の酒造好適米です。 酒米の雄「山田錦」を母とし、その特性を受け継ぎながら、土佐の気候・風土に合った酒米の研究を重ね、平成10年に誕生しました。 酒造適性試験の結果は山田錦にも劣らず、吟醸酒の出来も上々。 適度な酸味とフルーティーな香り、軽やかな旨み、飲み飽きないキレのよさで、県内外から高い評価を得ています。 ■風鳴子(かぜなるこ)高知で育てた酒造好適米の第2号として、平成14年に誕生しました。 高知県ならではの早期栽培に適した酒米として注目を集め、酒造適性も良好。 地酒志向が高まる中、独自性や個性ある酒造りに適した品種として、大きな期待を寄せられました。 一方で、米が割れやすいという加工上の課題があり、その改良を目指した新たな開発が「土佐麗」の誕生につながりました。 現在も「風鳴子」の優れた酒造適性に惚れ込み、技術力で欠点をカバーしながら、「風鳴子」の酒を造り続けている蔵もあります。 ■土佐麗(とさうらら)平成30年に開発された、高知県産酒造好適米の第3号です。 「風鳴子」は酒造適性に優れていましたが、米が割れやすいという欠点がありました。 その改良を目的として「風鳴子」を親として開発されたのが、この「土佐麗」です。 吟醸酒や大吟醸酒に使われるような高度の精米にも耐えられるように改良され、割れにくい特性を持ちます。 酒造適性も風鳴子と同様に優れており、味幅のある、しっかりとしたお酒に仕上がります。 
高知酵母
■KW-77株(平成3年開発)清酒酵母とワイン酵母を掛け合わせて誕生した酵母です。 ワイン酵母ならではの特徴的な香味と、清酒酵母由来の強い発酵力を兼ね備えています。 華やかで個性ある香りを楽しめる酒に仕上がります。 ■A-14株(平成4年開発)清酒酵母同士を細胞融合させて誕生した酵母です。 モロミでの発酵力やアルコール耐性が強く、酢酸イソアミルを多く生成し、アミノ酸量が少ないのが特徴です。酸がやや多く、しっかりとした飲みごたえのある酒に仕上がります。 ■CEL-19株(平成5年開発)カプロン酸エチルの生成量が多く、酢酸イソアミルはやや少なめです。 また、リンゴ酸を多く生成するため、爽やかな酸味が特徴です。 適度な酸味とフルーティーな香り、軽やかな旨み、飲み飽きないキレのよさで、県内外から高い評価を得ています。 ■CEL-24株(平成5年開発)カプロン酸エチルやリンゴ酸の生成量が、CEL-19の約2倍にもなる酵母です。 発酵力がやや弱く、日本酒度はおおよそ-15程度で仕上がるため、甘酸っぱく非常に香り高い低アルコール酒(アルコール13%程度)ができます。 開発当初は、淡麗辛口が主流だった高知県では珍しいタイプの酵母でしたが、そのフルーティーな香りに注目した1蔵が、この酵母の名を冠した酒を造り続けたことで、次第に注目を集めるようになりました。 現在では、県内13蔵がこの酵母を使用しており、日本酒愛好家だけでなく、これまで日本酒に馴染みのなかった層からも高い支持を得ています。 また、欧米の酒類のコンテストでも常に上位入賞を果たすなど、高知県を代表する酵母のひとつとなっています。 ■AC-17株(平成7年開発)発酵力が強く、酸は普通からやや高めです。 カプロン酸エチルの生成量はCEL-19の約半分で、酢酸イソアミルはやや多め。 酸味のきいた、バランスの良い香りと味わいが特徴です。 ■AA-41株(平成15年開発)A-14株をもとに、酢酸イソアミルの生成量をさらに高めるよう改良された酵母です。 酸はやや高めで、メロンやバナナのような香りを放ちます。 酢酸イソアミル系酵母の中でも香りの高さは全国的に見ても際立っており、国内外の市販酒コンテストでも高く評価されています。 ■AC-95株(平成19年開発)酢酸イソアミルとカプロン酸エチルの生成量がともに高い、全国的にも珍しいタイプの酵母です。 バナナとリンゴを合わせたような、パイナップルを思わせる香味が特徴です。 発酵力は強く、酸はやや控えめで、軽やかで爽やかな味わいの酒に仕上がります。
 ■高知の清流「四万十川」「仁淀川」「物部川」「吉野川」などの一級河川が流れ、水質の良いことで知られる高知の清流には、風土記の中で「神河と呼ばれ水が清らかなので大神に捧げる酒を造るためにここの水を用いた」という記述があります。 ■海洋深層水高知県室戸岬沖、水深370mから取水される深層水は、豊富なミネラル、清浄な海水、年間を通じての低温性などの特性を持つ極めて有用な資源です。 高知県工業技術センターでは深層水の製品開発を行い、特に深層水を仕込み水に使用した清酒醸造に大きな成果をあげています。 例えば、清酒の雑味成分であるアミノ酸は、深層水添加量が多くなるほど低くなります。 現在、県内の複数の酒造場において深層水を使った清酒が商品化され、「すっきりと飲みやすい香りのよい酒」として高い評価を受けています。 |